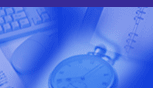

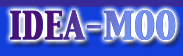
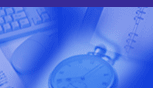 |
 |
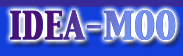 |
||||||||
|
井出薫
日本は色々な課題でジレンマに陥っている。 ガソリンの暫定税率廃止が実現する見通しになっている。インフレ目標2%を超えるインフレになっているのだから当然の措置だと言える。そもそも暫定税率はオイルショックで物価が急騰し道路財源が不足した際に導入された税であり残っていたことが不自然だった。一方、暫定税率が廃止されることでガソリン消費量が増えることが懸念される。今夏の猛暑が象徴するとおり地球温暖化問題は深刻化しており化石燃料の使用削減が喫緊の課題となっている。その点では暫定税率は化石燃料の使用削減に貢献していた訳で、暫定税率廃止は短期的にはメリットが大きいが長期的にはデメリットがある。だからと言って代わりの税を導入することには反発があるし経済に悪影響が出る可能性もある。 温暖化対策として再生可能エネルギーの活用が進められている。しかし太陽光発電や風力発電は時間帯、季節、気象条件などで出力が大きく変動し安定的な電力供給が難しい。現代社会において電力の安定供給は欠かせないが、火力で補ったのでは温暖化対策は進まない。だから他の方法で補うしかない。蓄電池を普及させ昼間に蓄電し夜間や雨天・曇天のときには蓄電池を使う方法が考えられる。だが、それですべてを賄うことは困難で、しかも蓄電池には有害物質が使用されているため廃棄の問題が付き纏う。水力や地熱、バイオ燃料、水素燃料などは安定電源となりえるが、水力や地熱は利用できる場所が限られ、バイオ燃料は食糧生産に損害を与える、あるいは森林伐採が進み自然破壊を進める恐れがある。水素燃料も製造や運搬が容易ではなく広く利用することは難しい。そうなると原発が最善の対策という意見が出てくる。実際、世界各国で原発の再評価が行われ脱原発を宣言したドイツでも見直しの動きがある。しかし、いくら安全対策を進めても事故のリスクはゼロにはできず事故が起きた時の影響が甚大であることに変わりはない。事故を防ぐことはできても高濃度放射性廃棄物の処理は容易ではなくしかも超長期に亘る安全な保管が必要となる。そのコストとリスクは大きい。このようにこの問題は容易には解決できない。核融合発電に期待する向きもあるが、実用化できるかどうか分からない。 死亡者数が出生数を大きく超え人口減少が止まらない。政府は少子化対策に力を入れているが、諸外国の例を見ても、それだけでは人口減少は止まらない。欧米各国は人口が増加しているが、それは大量の移民を受け入れているからで移民がいなければ日本同様人口減少を招いている。それゆえ人口減少を防ぐ最良の政策は移民受け入れ拡大と言える。現時点でも、移民が増えることで人口減少の速度が遅くなっている。ところが、日本では欧米よりも遥かに移民が少ないにもかかわらず、移民受け入れ拡大に反対する世論が強く、受け入れが進まない。参院選でも移民に対して厳しい政策を提唱する政党が軒並み票を伸ばしている。 日本の食料自給率は低い。カロリーベースで40%を切っている。食料は人間が生きていくうえで最も重要な財で、自給率の低さは安全保障上大きな問題となる。国内でも自給率を上げることを求める声が広がっている。しかし実現は容易ではない。自給率低下の大きな要因として食生活の変化がある。食の洋風化が進んだことで、日本国内で自給できる米の消費量が減り、代わりに日本の風土に合わず外国からの輸入に頼らざるを得ない小麦、畜産物、油脂類、家畜の飼料などの消費が増えている。その結果、米の減反政策が続き、代わりに食料品や飼料の輸入が増えた。食生活を戦前に戻せればよいが、3食とも米と魚、山菜、汁物という生活に今の日本人が耐えられるとは思えないし、自由主義社会でそのようなことを強いることはできない。それができたとしても自給率向上には農業人口を増やす必要がある。しかし今の若い人で農業に従事することを希望する者は少ない。それゆえ農業人口を増やすためには移民の大幅な受け入れ拡大が必要となるが先に述べた通り反発が大きく実現が難しい。さらに、日本は水が豊かな国という印象があるが違う。日本列島は縦に長く中央は山脈が連なっており平原が少なく山と海の距離が短い。そのため雨水はすぐに海へと流れだしてしまう。そのため農業振興には水の確保という重要かつ困難な課題がある。 インフレが進んでいることで、日銀は政策金利の引き上げを検討している。しかし日本のインフレは消費の活性化ではなくコスト増によるところが大きく利上げでインフレが収まるか分からない。利上げは円高に繋がり輸出産業の業績を悪化させ、住宅ローンの金利上昇で家計を圧迫する。だからと言って利下げをしたら円安でエネルギー資源の輸入価格が上がりインフレが加速する。ドル高を嫌うトランプ米国大統領も黙っていないだろう。 高等教育無償化は、より多くの者が高等教育を受けることができるようになるから良い政策と評価できる。家が貧しくて大学進学を諦めていた高校生には希望の光となるだろう。一方で財政問題を除いても課題がある。定員割れを起こしている高等教育機関が全国に多数存在する。無償化=行政機関による援助拡大で、教育の質も研究の質も低い高等教育機関が生き残り、やる気も学力も乏しい学生、卒業生が大量に生まれることになりかねない。それゆえ教育研究の質向上のための施策が欠かせないが人材面でも資金面でも難しい。 他にも日本は様々なジレンマを抱え込んでいる。これらのほとんどが容易には解決できない。解決のためには一般市民もある程度我慢が必要となる。政府、報道、市民すべてがこの現実をよく認識しておくことが望まれる。 了
|