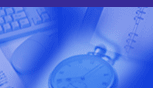

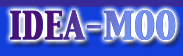
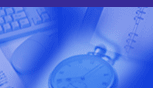 |
 |
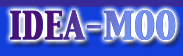 |
||||||||
|
井出薫
減税は消費の活性化を促し景気の回復に寄与する。バブル崩壊以降、財政赤字を理由に、アジア通貨危機に伴う金融危機時の小渕政権を除くと、消費者向けの減税で景気を浮揚させる政策はなかった。それが、小泉の構造改革、安部の異次元の金融緩和が十分な成果を上げられなかった原因の一つではないだろうか。 立憲民主を除く野党は減税を目玉に選挙戦に臨もうとしている。これを財政ポピュリズムと批判する声もあるが、選挙目当てだとしても減税は悪い政策ではない。基礎控除の引き上げにしろ、消費税減税あるいは廃止、いずれも実施する意義はある。 自国通貨で国債を発行している限りデフォルトは起きない。財政赤字と国債発行残高の増大は高度なインフレに繋がると緊縮財政論者は警告するが、バブル期以来の日本の財政状況と長期のデフレを考えると、高度のインフレが起きる可能性は低い。マネーストック(M2)が1200兆円以上もある市場で、財政赤字が10兆、20兆拡大したからといって高インフレになるはずがない。確かに、英国のトラス政権のように、減税と財政拡大政策が、財政危機に繋がるとの不安を招き通貨や国債の暴落を招いた例はある。それゆえ減税にリスクがあることは否定しない。特に消費税廃止は景気浮揚効果を考慮しても20兆円程度の税収減が予想され市場に不安が広がる可能性はある。 だが減税のリスクを和らげることはできる。そのために必要なことは経済成長を実現することだ。たとえば実質1.5%、物価指数1.5%、名目3%の成長を実現すれば24年間で名目GDPは倍になる。そうなれば、名目GDPの伸びと税収の自然増で対GDP比での国債発行残高は大幅に下がる。このような長期的見通しを立て、それを投資家たちに期待させることができれば、リスクは回避できる。 問題は経済成長を如何にして実現するかだ。各政党とも減税を訴えるだけで、成長戦略の具体的な政策がない。消費税廃止は短期的には消費を活性化し経済成長を促すが効果はすぐに切れる。基礎控除引き上げも効果は長持ちしない。成長戦略を描きそれを実現する政策があって初めて減税の効果が上がる。 そのためにはまず成長分野、研究開発、教育への投資拡大が欠かせない。ただし闇雲に予算を付けるだけでは成長に繋がらない。投資は多方面の知見を集めて十分検討した上で行う必要がある。さらに、成長には労働力人口の増大が欠かせない。労働生産性の向上には限界があり幾ら高度な技術を用いても十分な労働力がなければ成長は覚束ない。労働力人口の拡大には移民など海外からの労働者受け入れを大幅に拡大する必要がある。これには保守派など国内から強い反発が予想され、また文化の対立など社会に軋轢が生じることをある程度我慢する必要がある。だが、いずれにしろ成長には移民などの労働力が不可欠で、その必要性を国民に説得する必要がある。 減税は有益ではあるが、それだけでは不十分で投資拡大と海外からの労働者受け入れ拡大など成長戦略が欠かせない。そして各政党ともそれが欠けている。 了
|