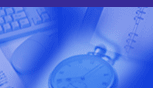

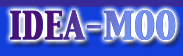
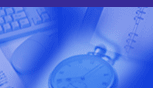 |
 |
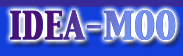 |
||||||||
|
井出 薫
ウィトゲンシュタインは遺稿『哲学的探究』で言葉の意味を知りたければ、その言葉がどのように使用されているかを調べなくてはならないと指摘した。この指摘は言葉の意味とは言葉の使用であるとする意味の使用説を主張しているようにも取れる。『哲学的探究』全体を読めば、後期ウィトゲンシュタイン哲学の特徴として挙げられる「安易に一般化(理論化)しない」という姿勢が徹底されており、ウィトゲンシュタインが言葉の意味の使用説を提唱している訳ではないことが分かる。だが、ウィトゲンシュタインの意図がどうあれ、「言葉の意味は、言葉がどのように使用されているかを丹念に調べれば分かる」という主張は検討する価値がある。なぜなら、生成AIの設計思想には暗黙裡に、「言葉の意味とはそれがどのように使用されているか統計的に調査分析すれば明らかになる」という前提があるからだ。現在の生成AIは膨大な量の文章を深層学習の手法を用い大規模言語モデルに従い統計的に処理分析し、言葉がどのように使用されているかを学習することで人間にほぼ等しい自然言語処理能力を獲得している。このことは、言葉の意味とは、言葉の使用の実態を知ることで分かるということを示唆している。 しかしながら、これには異論がある。「酸っぱい」という言葉がどのように使用されているかを生成AIは学習して人間とほぼ同じように使用することができるようになる。だが味覚を持たない生成AIは人間のように酸っぱさを感じることはない。一方、日本語を話す者は、生成AIが感じることがない「酸っぱい」を体験しているがゆえに、「酸っぱい」という言葉を自由自在に使用し理解していると考えることができる。それゆえ味覚を持たない生成AIは学習を繰り返しても、人間と完全に同等な自然言語処理能力を獲得することはできない可能性がある。この問題はしばしば記号設置問題と呼ばれる。つまり、「酸っぱい」という言葉が「酸っぱい」というリアルな感覚にどのように結びつくのかという記号設置問題は感覚器官を持たない生成AIには解決不可能で、そこに人間と生成AIとの差が残ってしまう。このことは、哲学的には言葉の意味とはその使用を調べることで解明されるという思想に疑念をもたらす。ウィトゲンシュタインは『哲学的探究』で言葉の使用説に近い立論を展開した後、感覚と感覚を表現する言葉の分析を行っている。これはウィトゲンシュタインが記号設置問題に等しい問題意識をもっていたことを示唆する。 しかし、このような議論にはポストモダニストの代表格デリダの支持者が反論するだろう。この議論は言葉に先立ち「酸っぱい」という感覚があり、それを表現するために「酸っぱい」という言葉を当て嵌めるという言語の対応説あるいは指示説という伝統的な哲学的ドグマに縛られている。事実はそうではなく、「酸っぱい」という感覚は「酸っぱい」という言葉と独立したものではない。「酸っぱい」という言葉を知ることで、その者の「酸っぱい」という感覚の在りようが変容する。つまり、感覚と言葉は不可分であり、言葉から独立した感覚などという者は存在しない。そして、両者の不可分性から、言葉の使用を徹底的に調査分析することで生成AIは言葉を人間と完全に同等な水準で処理することができるようになる。記号設置問題は哲学的幻想「言葉に先立つ感覚が存在するという幻想」に基づく疑似問題に過ぎない。 だがデリダ流の異論にも疑義がある。言葉を喋れない幼児でも酸っぱさを感じている。それは振る舞いから想像がつく。だからこそ酸っぱいという言葉を幼児は容易に学習することができる。脳の障害で言葉の理解や発語が困難な者でも酸っぱいという感覚を持っている。また話し言葉や書き言葉を知らなくとも、身振り言語で酸っぱいという感覚を表現することができる。このようにデリダ流の反論に再反論することは難しくない。 筆者はこの問題は哲学的な論争で解決することはできないと考える。もしウィトゲンシュタインが現代に生きていれば、筆者の考えに同意するのではないかと思う。つまり哲学的にはこの論争には答えはない。ただ論争があるだけなのだ。若き日の『論考』を著述した時代のウィトゲンシュタインであればこの論争を疑似問題として退けるだろう。ただしこのことは記号設置問題は疑似問題に過ぎないという立場が正しいことを意味するのではない。筆者の意見は、記号設置問題を重要な問題とする立場とデリダ流の立場をメタレベルで比較対照し、両者の優劣を哲学的に決定しようとしても不可能であることを示唆しているに過ぎない。 しかしながら、哲学的には疑似問題だとしても、現実的、技術的観点からすると、記号設置問題は重要な問題と言わなくてはならない。酸っぱいという感覚を持ち得ない生成AIは、やはりそこに言葉の使用の不自然さが残る可能性があり、それを科学的、技術的に吟味し不自然さを解消する必要がある。現在の生成AIの欠点とも言える人間とは比較にならないほどの膨大な量の学習が自然言語処理能力の獲得に必要になること、また過学習(学習し過ぎると自然言語処理能力が劣化するという問題)が起きることも、記号設置問題と関連している可能性がある。記号設置問題の考察は生成AIの改良や汎用AI(AGI)の実現に貢献すると期待してよいだろう。 生成AIの能力に関する諸問題は、哲学的な考察では解決できない。それは本質的に科学的、技術的な問題と言わなくてはならない。だからと言って哲学的考察が無意味だということにはならない。哲学的な考察は問題の所在を示し、研究開発にヒントを与え、その使用に当たって注意すべき点を明らかにする。またAI開発とその使用のあるべき姿など倫理的、社会的な問題を論じる際には哲学的な考察が欠かせない。 了
|