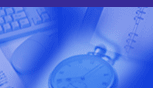

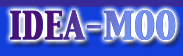
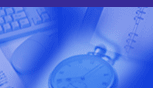 |
 |
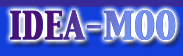 |
||||||||
|
井出 薫
社会と個人、どちらが先か、重要か。こういう議論がなされることがある。こういう問いは不毛な論争に終わることが多いが、哲学的にも、社会科学的にも、政治的にも一定の重要性があり無視はできない。そこで、存在論、認識論、実践論の三階層で簡単に議論してみる。 存在論的には、社会を実在として捉えるか(社会実在論)、名目的な存在に過ぎないと捉えるか(社会名目論)という議論がある。社会実在論では社会という存在はそこに属する個人から自律した存在者であり、それ独自で議論する必要があるとされる。社会有機体説などもこれに属する。一方、社会名目論では、社会は個人の集合体に過ぎず、集合体に対する名前に過ぎないとされる。社会学者では、デュルケムが実在論者で、ジンメルが名目論者などと称されることがある(ただし、この評価が正しいかどうかは疑問がある)。社会実在論では社会こそ第一次的な存在者であり個人は二次的な存在者と想定されることが多い。社会名目論では実在するのは個人であり、社会という概念は個人の集合体を語るための便宜的な記号に過ぎないということになる。それゆえ社会は個人と同じ意味では存在しない。さらに、この二つの立場の他に、社会も個人も実在するものではなく、実在するのはヒトという生物種の個体だけであり、個人も社会もヒトの集団の中で構成された二次的な概念に過ぎないという立場もある。個人という概念と「個人主義=(個人の自由を至高のものとする)自由主義」という思想が確立されたのは近代西洋においてであり、それ以前、それ以外の地域では近現代的な個人という概念は存在していない。それゆえ、個人も社会も実在者とは言えず生物学的個体だけが実在者だという立場も決して極論ではなく、自然主義などにはこれに近い立場がある。実在という概念をもっぱら恒星や惑星、私たちの周囲にある物、原子分子など物理的実在と捉えるのであれば、個人も社会も構成された便宜的な概念だとみることができる。しかし、存在論を語る場合、存在とは、そこで様々な思索や実践がなされる場として想定されており、もっぱら生物としての個体のみを真の存在であり、個人や社会を二次的な構成された存在とする立場は狭すぎる。それゆえ、存在論的には、個体、個人、社会、いずれも存在者であるが、存在の意味合いが異なると捉えるのが妥当だろう。G・ライルは『心の概念』でカテゴリーミステークという思想を展開した。大学の学生、教員、校舎、所有する様々な施設などは大学を構成する不可欠な要素であるが、大学そのものとは異なる。これらを見学した人が「校舎、施設、学生たち、教員たちを見学させてもらいましたが、大学(そのもの)を見学していません」と言ったら、案内人は肩をすぼめるしかない。大学は校舎や学生とはカテゴリーが異なる。だが、それでも大学は存在する。個人と社会も同じで、それぞれカテゴリーが異なるが存在する。ただし、それでも、個人か社会か、あるいは生物学的個体かという問いには、後述する認識論や実践論との関りにおいて重要性があり、それを空疎な議論として切り捨てるべきではない。 認識論的には、個人か社会かという問題は、様々な社会現象を、個人から見るか、社会全体から見るかという方法論的な対立として現れる。資本主義社会で主流となっている現代経済学では、(所与の情報を基に)自由かつ合理的に判断し行動する個人を方法論的な出発点とする。企業など法人、政府なども意思決定の主体とされているが、これらの集団の意思決定は、集団の中核となる個人の意思決定の総和として表象されており、その意味で個人の意思決定が集団を動かすと想定されている。ここ数年来話題になることが多い行動経済学は、主流派経済学が合理的な選択を重視するのに対して、合理的とは必ずしも言えない各人の行動に着目する。しかし、それでも個人が中心であり出発点であることに変わりはない。ゲーム理論も他者の意思決定との関りが重視されるが、それでも個人が中心である点では主流派経済学と変わるところはない。マクロ経済学は個人ではなくマクロな経済指標の分析を行い、それに基づき理論を展開するが、個人主体のミクロ経済学やゲーム理論、行動経済学を基礎として、統計学的な視点を導入したものとみなすことができる。それゆえ、マクロ経済学でも個人が出発点となっていると言ってよい。一方、マルクスは労働者は労働の担い手である限りにおいて労働者であり、資本家は資本の担い手である限りにおいて資本家であるという。この言葉は、マルクスが社会全体の動きを第一次的な存在としていることを示す。マルクスは、抽象から具体へと研究を展開することこそが科学的な方法であるという。そして、労働者ではなく労働、労働が生み出す商品と貨幣、資本家ではなく商品と貨幣から発展した資本など抽象的な概念とその分析が研究の出発点となる。その出発点にあるのは、自由な選択をする個人ではなく社会全体を抽象化して得られる概念だと言ってよい。ただし、ヘーゲルと異なりマルクスではこの抽象化された概念はあくまでも科学的な認識を得るための手段であり実在の要素ではない。その意味で、マルクスは認識論的には社会を第一次的な存在とするが、存在論的には微妙なところがある。ただし共産主義革命を歴史の必然とするマルクスはやはり基本的に社会を存在論的にも重視していると言える。経済学以外の社会科学や人文科学でも、個人を出発点とする立場と、全体としての社会を出発点とする立場がある。前者は個人の心理学的な考察を重視し、後者は統計学的な考察を重視する傾向がある。このように認識論的にも、社会を重視しそれを出発点とする立場と個人を出発点とする立場がある。一般論的としてどちらが正しいかを決めることはできない。個人から出発することが望ましい領域や問題もあれば、社会から出発した方がよい領域や問題もある。また、どちらから出発しても最終的には収斂して同じ帰結が得られることもある。また両方の立場を併用する必要がある場合もある。いずれにしろ哲学的考察で優劣を決めることはできない。哲学にできることは様々な方法を記述し比較評価し、時には新しい方法論を提唱することに限られる。だが、それでも、そのことが独断的な思考や帰結を避けるために有益なことは多い。なお、生物学的な個体から出発して個人の活動や社会現象を説明しようとする立場もあるが、そこには自ずから限界があり、自然科学的な理論やデータ、数理モデルなどが社会科学でも有益な道具として使用できる場合があるということに留まる。物理学や生物学で社会がすべて理解できるなどという思想は誤りで、そこまで極端な主張をする論者はいない。 さて、最後に実践論的な階層について簡単に触れておく。実践においてこそ、個人か社会かが最重要な課題となる。どちらをとるかで個人主義・自由主義対社会主義・共同体主義という対立が生じる。もちろん、個人主義と社会主義という対立軸だけで政治的な立ち位置を評価することはできない。個人主義・自由主義には社会民主主義など左派と新自由主義など右派があり両者の隔たりは大きい。社会主義・共同体主義でも共産主義という左派と、国家主義という右派との対立は極めて激しい。日本でいえば、共産党と参政党は共に社会主義・共同体主義に属するが、最も政治的には遠い位置にある。それでも、個人主義と社会主義という分類は政治行動や政治的主張を理解するうえで欠かせない。そして、このような政治的対立があるからこそ、それを背景として存在論的な階層並びに認識論的な階層でも個人か社会かという論争が起きる。 存在論、認識論、実践論、それぞれの階層で個人と社会という問題を論じてきた。しかし、三つの階層で分けて論じることができるとは言え、本稿での考察から分かるとおり三つの階層での論争は重なり合っている。それゆえ一つの階層で考えていただけでは問題の全体を把握することはできない。しかしながら、いきなり全体を把握しようとすることは現実的ではない。そのようなやり方では迷路に迷い込むことになる。それゆえ、第一段階として各階層で議論する意義は大きい。そして、その成果から全体へと進む必要がある。 了
|