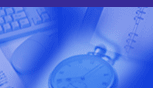

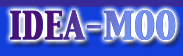
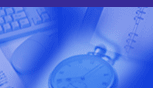 |
 |
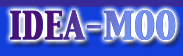 |
||||||||
|
井出 薫
各地で熊が出没して被害が出ている。自治体は人を襲った熊、襲う恐れがある熊を射殺するなどして駆除する。すると駆除した自治体にクレームが来て職員が対応に追われている。人を襲った熊や住宅街に出没して人に危害を加える恐れがある熊を駆除するのはやむを得ない。確かに熊に悪気がある訳ではなく可哀そうではある。しかし人の命を危険にさらすことはできない。そういう場合、熊の射殺もやむを得ない。人も動物の一種で命を守るために懸命に行動する。その現れとして見るべきで、熊が可哀そうだと言って自治体を非難するのは筋違いだ。一方で、大規模な掃討作戦を実行して熊を絶滅させるべきだ、熊と人間は共存できないという過激な意見があるが、これもまた賛同できない。75年に初版が出版されたオーストラリアの哲学者ピーター・シンガー著作『動物の解放』に記されているように、全ての動物は等しい権利を持っている。人間は地球上の生物進化の過程で、他のすべての動物と同じ共通の祖先から進化した。人間は決して他の動物より優れている訳でもなければ、他の動物の生殺与奪の権限を与えられている訳でもない。生存競争の結果として支配的な地位を占めているに過ぎない。それゆえ、危害を加える恐れがない動物を無暗と殺すことは許されない。熊を日本列島から隈なく駆除しなくても人間は十分に安全に生きていける。熊に殺される者がいるのは事実だが、人に殺される者の方が遥かに多い。さらに日本では殺人より自ら命を絶つ者の方が遥かに多い。熊の存在が理由で自殺する者がないとは言い切れないが、あったとしても極めてまれな例でしかない。況や、熊だけが食べる毒入りの餌を大量に散布する、熊にのみ感染し致死率100%のウィルスを合成して散布することなどは到底容認できない。危害を加える、加える恐れがある、個体数が増えすぎて生態系を破壊する、などの正当な理由がない限り、殺害するべきではなく、互いにテリトリーを守ることで静かに共存できる環境を整備することが強く望まれる。また駆除する場合でも、可能な限り熊の苦痛が少なくなるような方法をとる必要がある。 動物の生存権を尊重することと生態系の保全の重要性はシンガーの著作や環境保護団体の活動などを通じて広く認識されてきている。だが哲学的に考察し解決すべき課題は多数残されている。 そもそも、なぜ動物の解放、権利、福祉を考える必要があるのか。それぞれの生物種にはそれぞれの生き方があり、人間以外の動物は他の動物の権利や福祉など考慮しない。肉食獣が被食動物の生存権に配慮していたら飢え死にする。どの種も、どの個体も自らの生命を維持することを第一に行動する。人間とてそれは変わらない。人間は高い知能を持ち、それゆえ文明を構築して人口を増やしてきた。そして、動物を捕まえて料理する様々な方法を考案し、豊かな食生活を実現している。それでよいではないか。なぜいちいち動物の権利や福祉を考えないといけないのか、人間以外の動物は他の動物の権利や福祉など決して考えないではないか、人間だけが何故それをしないといけないのか。この問いには、人間だけが生きていくために必要な量を遥かに超える量の動物の殺害を行なっていると答えることができよう。野生時代の生存ぎりぎりの状態で生きていた時代には人間もまた数の限られた他の動物を狩り生き延びる以外の方法はなかった。だが、文明が誕生して以来、人間は余りにも多くの無益な殺戮を行なってきた。儀式のためだけに動物を殺したり、遊興のためだけに動物を殺したりした。また、近代以降は、食べられる部位のすべてを食べるのではなく、美味しいところだけを食べ、残りは捨てることが格段に増えた。その結果、必要以上に大量の動物が殺されている。さらに文明の発展と共に人間の都合で自然環境が著しく改変破壊され、多くの種が滅んだ。絶滅種の数はカンブリア紀以降に起きた5回の生物大量絶滅と同じ規模と言われ、今なお人為的な活動が多数の生物種を絶滅に追いやっている。それが人新世という新しい地質時代の区分が設けられた理由でもある。このように、生きるために必要な限度を遥かに超えて、人間は多くの動物を殺し絶滅させ、今また絶滅の危機に追い込んでいる。さらに家畜という形で動物たちの自由な行動を著しく制約している。動物を生命体として尊重することなく単なる道具として扱っていると言ってもよい。しかしシンガーが指摘するとおり、人間にそのような振る舞いをする自然的な権利などない。なぜなら人間も生物進化の過程で偶然誕生した一生物種に過ぎないからだ。人間は地球上で唯一の知的生命体であり、理性を持ち、複雑で高度に分節化した言葉を使用するがゆえに地球上で卓越した存在であり、他の動物とは質が違う、だから人間は動物を支配する権利があり、人間以外の動物は人間に奉仕するために存在するという考えが昔はあった。だが、人間が他の動物とは異質な性質を持つことは事実でも、そのことは他の動物の権利や福祉を無視することを正当化するものではない。そのような理屈を持ち出すならば、将来、人間よりも遥かに高い知能と科学技術を持つ生物種や宇宙人が地上に現れたら、人間はその者に支配権を渡し、その者が望めば奴隷として扱われることを甘受しなくてはならないことになる。しかし、そのようなことは認められるはずがなく、人間は自分たちの生存権と自由権を主張する。他の動物も同じでただ生存権と自由権を人間のように主張する術を持たないに過ぎない。人間のような理性と言葉をもっていなくとも、動物は快楽と苦痛を感じる能力があり、その能力を持つということが生存権と自由権を尊重すべき根拠なのだ。そのことを明確に主張したのが功利主義者のベンサムで、ベンサムの主張は長く無視されてきたが、20世紀後半に評価され、動物の権利や福祉に関わる議論では今では支配的な思想となっている。人間より遥かに高い知能を持ち、その知能が人間には想像もつかないようなものだったとしても、人間はそのことを以て自らの生存権と自由権を放棄しないしするべきでもない。人間も他の動物も、そして、その超知的生命体も快楽と苦痛を感じるという点で共通しており、そして、その点において生存権と自由権、快適に暮らす権利を持っている。たとえどんなに高い知能を持っていても、AIには私たちは生存権や自由権を与える気にはならないし、与える必要もない。AIは快楽と苦痛を感じない。感じているような振りをすることができるに過ぎない。また、AIはソフトウェアを移植することで幾らでも同じものを作り出すことができるが、人間も動物もその個体は一回限りの有限な生を持つ存在、つまり唯一無二性を持つ存在でありAIのように複製できるものではない。 (注)AIは快楽と苦痛を感じないとしても、AI機能を具備した快楽と苦痛を感じるロボットを作ることができるのではないか。そういうロボットには権利や福祉を考えるべきではないかという意見があるかもしれない。しかし、ロボットはあくまでも金属やプラスチックからできた無機物であり人間や他の動物のような快楽と苦痛を感じることはあり得ない。快楽と苦痛は生命と密接に関連しており、生命を持たないロボットは快楽と苦痛を持つことはなく、ただ快楽と苦痛の振る舞いを模倣することができるに過ぎない。たとえば人間の痛みを感じる脳神経系の構造と機能をシミュレーションして、それと論理的に等価な活動を実行することはできる。だが、それはあくまでもシミュレーションに過ぎず、人間や動物が感じる快楽や苦痛とは同じものではない。それは対象とモデル・道具との関係にあり解消できない差異がある。つまりロボットはどこまで行ってもロボットであり人間や動物とは解消できない差異を持つ者として存在する。また、AIと同様にロボットも複製可能であり唯一無二性は存在しない。 野生動物ではなく家畜の権利や福祉をどう考えるかという問題がある。シンガーはベジタリアンであり、家畜は労働する仲間、共同生活する仲間として大切に扱うべきと考えている。そのため肉食は基本的に認めない。しかし、人間という種は元来雑食性で動物も植物も食べて生きている。植物だけでも健康を維持することができると主張する者がいるが明確な根拠はない。また動物を食べないと生きていくことが難しい地域もある。それゆえ食糧生産を目的とする畜産業も容認されると考えるべきで、全員がベジタリアンになるべきだとする主張には賛同しがたい。ただし、過酷な環境で飼育することは可能な限り避ける必要がある。十分な運動ができ居心地の良さを感じられるような環境を用意することが人間の義務だと言える。とは言え、現時点では狭い限られた場所で大量の飼育がおこなわれており、また、そうしないと十分な食糧を確保・供給できないという現実もある。また広い場所で放し飼いをする場合衛生上の問題が生じることがある。鶏などは放し飼いにすると産んだ卵に糞が付着するなどの問題が生じやすく、生卵を食する日本の場合などは衛生上の課題が生じる。それゆえ、現実に即した解決策を考える必要がある。但し家畜の権利と福祉に配慮し、家畜たちの苦痛を最小限に留める努力は決して欠いてはならない。 問題は他にも多数ある。たとえば研究開発にどこまで動物を使ってよいのか、使う場合どのような使い方が許されるのか、人間のクローンを作ることには強い倫理的な批判があるが動物のクローンを作ることは問題がないのか(すでに作成されているが)、など多数の議論すべき課題がある。ここでは、一つだけ取り上げよう。その問題とは、どの範囲の動物まで権利や福祉を尊重すべき対象と見なすかという問題だ。人間の最愛の友人である犬や猫、人間に近い類人猿、知能の高い猿やイルカ、鯨などは議論の余地はほとんどない。哺乳類や鳥類の多くも対象としてよいだろう。だが害獣の場合はどうか。しばしば病原体を媒介するネズミ、蝙蝠などにもその権利と福祉を尊重すべきだろうか。この問題に対しては、時と場合によるとしか答えられない。およそすべての野生動物は状況により人間にとって害獣となりうる。また、逆に害獣が有益な存在となることもある。では、爬虫類や両生類、魚類はどうだろう。魚は痛みを感じないと言われていた時代があった。だから釣り人が魚に同情する必要はないと言われた。だが、近年の研究は魚もまた痛みを感じると考える方が妥当だとする証拠を多数発見している。となると、爬虫類、両生類、魚類なども権利や福祉の対象となる。タコが高い知能を有することを示した研究があり、それを考慮するとタコやイカなども対象とするべきということになる。動物の中で最も種類が多い昆虫はどうだろう。「一寸の虫にも五分の魂」という諺があるが昆虫も痛みを感じるだろうか。昆虫が痛みを感じるかどうかは議論が分かれている。おそらく種により答えは分かれると想像される。また、苦痛や快楽を感じる動物にはすべて権利や福祉を考慮する必要があるのかという問題もある。先にも述べた通り害虫などは苦痛や快楽を感じるとしても、その権利や福祉を考えることには限界があり、人間の権利を優先するべきということになる。たとえば病原体を媒介する蚊などが該当する。逆に苦痛や快楽を感じない動物については権利や福祉を考慮する必要は全くないのかという問題もある。これには貝、ナマコ、ウニなどが該当する。このように、権利や福祉を考えるべき動物の境界を定めること、定めるための基準を決めることは難しい。一般論はなく、具体的な事例に即して考えるしかない。 (注)痛みなど苦痛、快楽などを動物たちが感じているかどうか、どうやって知るのかという問題がある。感覚や感情は主観的なものであり、痛みの振る舞いと痛みとは違う。一般的には、動物の振る舞いが人間の苦痛や快楽を示す振る舞いと類似している、人間の痛みに関連している脳神経組織とその働きに相当する構造や機能が研究の対象である動物に存在する、この二点が判断基準となる。ただし、この二つの基準に合格することを以て、快楽や苦痛を感じているように振舞っているだけで本当は感じていないという可能性を完全に否定することはできない。だが、それを言えば、哲学的ゾンビつまり振る舞いも構造も組織も普通の人間と寸分違わないが感覚や感情を含む意識を全く有しない存在を論理的には否定できないことから、他人が本当に快楽と苦痛を感じているかどうかは分からないという議論も成り立つことになる。だが、私たちは他の人も自分と同じように快楽と苦痛を感じる存在であり哲学的ゾンビなどではないと確信している。それゆえ、人間以外の動物も二つの判断基準を用いて判定することが現実的で妥当だと言えよう。−ただし、それが厳密な証明ではないことは否定できない。なお、感覚や感情など主観性の存在は自然科学や数学などのモデル・道具では解明することができない問題だと筆者は考えている。 このように、動物の権利や福祉に関してはたくさんの議論すべき課題があり、そのいずれについても完全なコンセンサスが得られているとは言えない。しかし、いずれにしろ、動物の権利と福祉を論じることは、生命の本質、生態系の保全、現代社会の在りようと未来の社会のあるべき姿などを考察する際に欠かせない。また、動物の権利や福祉を考えることは、人間の道徳的改善にも貢献する。 了
|