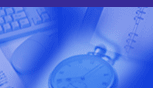

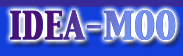
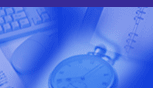 |
 |
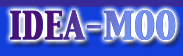 |
||||||||
|
井出 薫
最強のAI将棋は名人にも優る。藤井7冠でも最強のAIには勝てない。だが棋士はAIより明らかに優れている。なぜなら、対局場まで歩いてやってくることができるからだ。AIは人間が端末を対局場に設置しサーバとネットワークで繋がないと対局できない。将来、AIが人間の頭蓋骨に入るくらい小型化してロボットに装備され、ロボットが対局場に自力でやってくる日が来る可能性はある。しかし、そこに至るまでには解決すべき技術的な課題が無数にあり、いつ実現できるか、そもそも実現可能か現時点では予測も付かない。たとえば筆者が暮らす家具やら電化製品やら本やらが雑然と散らばっている狭くて古い木造家屋から最寄り駅まで歩き、電車に乗車し、千駄ヶ谷駅で下車し、千駄ヶ谷駅そばの将棋会館まで歩いてたどり着くロボットを作るとしよう。どれだけ解決すべき課題があるか、容易に想像がつくだろう。家の中からドアの鍵を開けて家の前の道路にでることすら現在のロボットにはできない。駅に向かう経路は頭の中に入っていても、道には人間ならば容易に避けることができるがロボットには避けるのが難しい障害物が満ちている。道路の段差や水溜りで転倒したり、自転車と接触して転倒したり、相手を転倒させて救急車を呼ばなければならなくなったりして、ほとんどの場合駅までたどり着けない。たくさんの人が向こう側から歩いてきたときも人間の側で避けてやらないと先には進めない。人間と同等あるいはそれ以上の自然言語処理能力を持つAIを作るよりも対局場まで歩いていけるロボットを作る方が遥かに難しい。人間はこれまで自分たちを知的生命体と自負してきたが、人間の優位性は知能ではなく身体にある。容易く自宅から将棋会館にまで行くことができるその身体こそ、人間の本質をなす。知能はそれを補佐する一つの機能でしかない。知能は身体の壁を超えることはできない。他者とのコミュニケーションと情報の送受で、知能は他者に影響を与え、様々な財や道具を生み出すことができる。それを身体を超える知能の働きとして捉えることができるように思えるかもしれない。しかし、コミュニケーションも情報の送受も身体なしにはできない。コンピュータ間の情報の送受、情報処理も、人間の身体が関わることで初めて意味を持つ。 身体の壁は感覚にも現れる。「酸っぱい」という概念をAIは書物や写真、新聞雑誌・テレビ・ラジオ、ネットの情報などから学習することができる。果物を見せ「これは酸っぱいと思うか」と尋ねると概ね妥当な答えが返ってくる。だが、AIは決して「酸っぱい」という感覚を直接体験することはできない。酸っぱさを体験するには人間と同じ味蕾を有している必要がある。しかしAIやロボットには味蕾は存在しない。味蕾の代わりに化学物質を分析するセンサーを装備することはできるが、それは味蕾を通じた人間の体験とは異なる。人間の体験は人間でないとできない。AIはただ学習したデジタルデータを基に回答のためのシミュレーションをしているに過ぎない。そこには自らの体験に基づく語りはない。人間は言葉を使って「酸っぱい」という体験を共有できるが、それは身体があるからで、AIが「酸っぱい」という概念を共有することとは全く性質が異なる。AI間で行われていることはデジタルデータの共有でしかない。 さらに、想像力と創造力でも知能は身体の壁を超えることができない。私たちは現実には存在しない人物や生物、構造物、見たことのない恒星や惑星、ブラックホールなどを想像することができる。新たな文学、音楽、絵画などを創造できる。だが、想像と創造には限界がある。超弦理論では物理世界は10次元時空だとされるが、10次元時空は数学的記号を使って表現することができるだけで、想像することはできない。射影などの手法を使って人間の感覚で把握可能な部分空間を描き出すことはできる。しかし、それは10次元時空そのものではない。それは10次元時空を4次元時空に分解することで直観的に分かりやすくするための補助教材でしかない。10次元時空を想像すること、直観的に把握することは人間の身体の性質から不可能なのだ。蝙蝠は超音波を発しその反射波を捉えることで周囲の空間を認識していると言われる。しかし、人間には蝙蝠の感覚を想像することはできない。疑似的に蝙蝠の感覚らしきものを体験することはできる。しかし、それは所詮人間の感覚に沿ってデフォルメしたものに過ぎず蝙蝠のそれではない。 人間の本質はその身体にある。知能は身体の活動を支える機能の一つに過ぎない。AIはいずれ人間の知能のおそらくほとんどすべてを模倣し、課題によっては人間より遥かに巧みに処理することができるようになるだろう。しかし、AI搭載のロボットでも、人間の身体と身体に生じる感覚、感情、思考を体験することはできない。それゆえに、それらを正確に模倣することはできない。 人間はその知能にこそ人間の本質があると考えてきた。しかし、AIとロボットの登場で、人間の本質は知能ではなく身体にあることが明らかになった。そして身体にこそ人間の本質があることを知ることで、人間はAIやロボットではなく、動物の一種であること再確認する。そのことを考えるとき、私たちは動物の福祉や権利に配慮する必要があることを知る。同時にAIやロボットに対しては同じような配慮は不要であることも分かる。将来、人間や他の動物にそっくりで優れた知能や行動力を持つロボットが登場する日が来るかもしれない。そのときには、共同体がそのロボットに人間と同等の権利を与えるという決定をなすことはありえる。そのこと自体は別に悪いことではない。それでも、どんなに優秀であっても、AIやロボットを、人間はもちろん他の動物よりも上の存在と考えるべきではない。身体とは生命体を意味し、人間における身体の本質性は、私たちが何よりも生命ある者を優先すべきことを教えている。そして、生命を根源的に尊重することを通じて、AIやロボットには存在しえない人間の尊厳が保証される。また、人間の本質とその尊厳が身体=生命性にあるということは、人間は動物だけではなくあらゆる生物と本質的な共通点を持つことを意味する。それゆえに、人間は生態系の保全に努める義務がある。AIとロボットの進化は産業と経済に大きな貢献をし、生活の利便性を高める(同時に様々な災厄をもたらす)。しかし、AIやロボットの文明的な意義はそれに留まることはなく、人間の本質=身体であることを認識させることにもある。 なお、人間はその身体を延長しようとする性向を持つ。それが原初的な技術として結実する。原初的な技術は身体の延長として現れるが、それは身体の壁の内部にあり、それに関わる知能も身体の壁を超えることはない。ただし、技術が高度化すると、技術とその産物は身体を離れ外部化する。その段階に至ると知能は外的なアルゴリズムとして形式化され共同体で共有されることになる。だが、そのアルゴリズムもまた身体との関りにおいてのみ意味を持つ。 了
|