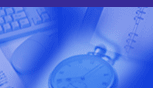

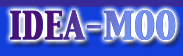
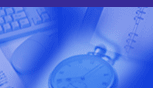 |
 |
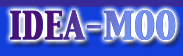 |
||||||||
|
井出 薫
労働とは、労働者がその肉体と頭脳を使って共同体とその成員に必要な財とサービスを生み出す活動を意味する。共同体の社会経済活動において労働とそれを生み出す労働力はなくてはならない存在であり、共同体の在り方に大きな影響を与えている。将来、技術が進歩し、ロボットが何でもできるようになり労働が不要になる時代が来るかもしれない。しかし、それが可能であるとしても、遠い未来の話しで、現時点では、労働は共同体を維持するうえで欠かせない。また、そのような時代が到来しても、共同体を健全に運営し成員の健康を維持するには少ない量でよいから労働を行なうことが望ましい。 労働の評価を巡っては対立する見解がある。マルクスは共同体を支えているのは資本家ではなく労働者であり、労働者こそが社会の主人公となるべき存在と論じ、労働を称えた。一部の神秘的思想家たとえばシモーヌ・ヴェイユもまた共産主義とは別の観点から労働を称えた。一方、アリストテレスなど古代ギリシャの賢人たちやハンナ・アーレントは、労働を共同体にとって必要不可欠なものであることは認めながらも、労働は生理的な欲求に基づくものであり、人間の能動的な活動においては低位にあるものと論じる。たとえばアーレントは人間の能動的な活動を、労働、仕事(設計や発明など共同体における成員の生活の枠組みを構築する活動)、政治的活動(共同体の諸問題を市民が集まって議論すること)の3つに分け、労働を最下位、政治を最上位に位置付けた。そして、アーレントは、マルクスは労働を過大評価しそれが独裁的な共産主義に繋がっていると批判する。確かにマルクスは労働を過大評価している。労働者が権力を掌握しただけでは豊かで平和で公正な社会は実現しない。公正な政治制度があり、教育が行き届き、科学技術が発達しそれが適切に活用されていることが理想的な社会を作るうえで欠かせない。一方で、アーレントは自分が生きていられるのは、彼女が使う生活必需品を作り、運び、廃棄物を処理する労働者たちがいるからであり、また彼女が本を書き出版できるのは印刷工場や製紙工場で働く労働者がいるからであるという事実を軽視している。労働はアーレントが言うよりずっと重要で政治や仕事の下位に位置付けることは適切ではない。そもそも労働と仕事と政治という区分は恣意的で、自説を正当化するための手段に過ぎない。それゆえ、マルクスとアーレントの見解を折衷して、労働は共同体が維持されるうえで最重要な存在であるが、それが共同体のすべてを決める訳ではない、と評するのが適当と言えよう。 (注)「社会」という言葉は本稿では、共同体とその成員、成員の諸活動、成員間並びに成員と財の連関など、様々な要素を含む(「共同体」より)広い概念として使用する。因みに「社会」の定義は論者によって様々で一致した見解はない。たとえばアーレントでは「社会」とは私的領域である家政(経済)が公的領域に侵入して生じた領域を意味する。しかし、一般的には「社会」という概念は本稿と同様に様々な要素を包含する広い領域を示すものとして使われる。 では、労働とはどのようなものであろうか。労働の要件を考えよう。労働は道具を必要とする。また労働には働きかける対象がある。生産の要素として労働力と生産手段(労働手段と労働対象)が挙げられることがあるが、このことに対応している。第一次産業や第二次産業に従事する労働者は言うまでもなく、作家など芸術家やスポーツ選手も様々な道具を使う。作家は昔はペンや鉛筆、タイプライター、今ではパソコンなどIT機器を使って作品を生み出す。古代には口承文学が広く存在したが、誰かがそれを文字に書き留めたからこそ現存している。また口承文学でも、それを人から人へと伝えるには、伝えるために相応しい人工的な場所と施設が必要でそれも道具の一つに数えることができる。昔も今も労働と道具は不可分な存在だと言えよう。さらに労働には対象が必ず存在する。第一次産業と第二次産業では、自然並びに自然から得られる食物や鉱物、半製品などが労働の対象となる。第三次産業では人と組織が対象となる。 労働には道具と作用する対象の他にも不可欠で重要なものがある。自然環境と社会環境がその例で、有毒ガスや放射性物質が充満した環境では誰も労働することができない。水不足や極度に高い気温あるいは低い気温のもとでは労働は困難になる。危険な感染症が蔓延したら労働の制限が必要になる。労働が円滑に行われるためには適切な自然環境が欠かせない。同様に労働には適切な社会環境が不可欠で、たとえば必要な訓練がなされていないと労働者は十分に能力を発揮することができない。不当労働行為が蔓延したら労働者は安心して労働することができない。労働が労働たり得るには良き自然環境と社会環境が欠かせない。 さらに、労働には適切な(情報通信ネットワークを介したものを含む)コミュニケーションが必要となる。農場や漁場では労働者たちは適宜仲間とコミュニケーションしながら作業を遂行する。それにより大きな果実を得ることができる。工場では労働者同士、労働者と技師、管理者との間で適切なコミュニケーションがなされていないと事故が起きたり不良品ができたりする。サービス産業では、コミュニケーション自体が労働の道具であり対象でもある。 このように、労働の現場には、道具、作用する対象、自然環境と社会環境、コミュニケーションなど複数の要素が存在する。それゆえ、労働の現場は、道具や自然環境との関わりにおいて科学と技術の発展の源泉であり、社会環境とコミュニケーションにおいて政治活動や社会的諸制度の生みの親となっている。その意味で、アーレントの労働に対する評価は不適切であり、労働を高く評価する者たちの思想には一定の合理性がある。しかし、労働が全ての出発点ではない。道具、作用する対象、自然環境の多くは労働の外部から偶然にもたらされたものであり、社会環境やコミュニケーションの多くは労働そのものとは独立して発展している。労働力と生産手段からなる生産力とそれに規定された生産関係が歴史の原動力(下部構造)であり、政治、法、文化、イデオロギーなどはその土台の上に立つ上部構造であるとみなし、下部構造が上部構造を決定するという教条主義的マルクス主義は正しいとは言えない。労働は上述のとおり様々な外部要因に影響されている。そのことを反映して、上部構造と下部構造は相互に影響しあい全体をなしており、下部構造で全てが決まるわけではない。 纏めるとこうなる。労働が共同体のすべてを決定する訳ではないが、労働は共同体の生理的、物質的欲求を満たすだけのものではなく、制度的、精神的、文化的諸領域を含めて共同体そのものの再生産と進化において最も重要な働きをなす。そして、このことを含めて労働の持つ多彩な側面と性質を解明することが、未来を展望するうえで欠かせないと考える。 了
|