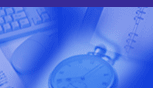

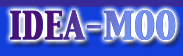
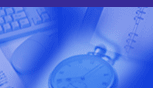 |
 |
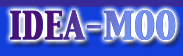 |
||||||||
|
井出 薫
犯罪の成立条件の一つに「意図的であること」が挙げられる。予期せぬ突風で転倒し他人の所有物を壊しても罪にはならない。では「意図」とは何なのか。 「手を上げる」と「手が上がる」は違う。前者は意図的な行為であり、後者は意図的ではない。では、両者の差とされる「意図(的)」とは何か、その有無をどのように判断するのか。ナイフを購入し人を付けて背後からナイフで切りつけたら、当然、意図的だと判断される。勝手に手と足が動いたと言っても通用しない。一方、身体がぶつかり意図的かどうかで喧嘩になることがある。いずれにしろ、人々は常識的に意図的であるかどうかの判断をしており、厳密かつ客観的な判断基準を持っている訳ではない。だから判断に迷うことがある。 他人の行為が意図的かどうかの判断は難しいが、自分のことなら容易に判断できる。手が意図せず動いてナイフで人を切りつけることなどない。多くの者がこう考える。しかし、薬物、病気、パニックなどで勝手に手足が動き他人に危害を加えることはありえる。それゆえ、他人は勿論、自分の行為ですら意図的かどうか判断が難しいことがある。 意図的行為と意図的でない行為では、脳の反応が異なるという意見がある。意図して手を上げたときと、意図せず手が上がったときとでは、外から見た振る舞いは同じでも脳内の反応が異なる。それゆえ、もし脳の個々の神経細胞レベルでの詳細なモニターができれば(現実にはできないが)、意図的であるかどうかが科学的に判断が付く。このような意見は正しいだろうか。次のような例を考えてみよう。ある男が別の男を付けナイフで切りつける。加害者は意図的ではなく勝手に手足が動きナイフが相手の身体にあたったと主張する。そのとき、加害者の脳の活動を神経細胞レベルまで詳細にモニターしていたとする。すると、意図的な行動をとる時に現れるパターンが加害者の脳では現れておらず、むしろ、意図的ではない行動をとる時の特徴が現れていることが判明する。さて、それでは、加害者の行為は意図的ではなく、無罪放免、精々民事上の責任が問われるだけということになるのだろうか。警察の捜査の結果、ナイフは犯行前日に購入されたものであること、加害者と被害者は金銭問題で揉めていたことが判明する。加害者は警察官の尋問に対してもしっかりと返答しており心神喪失や衰弱を疑う余地はなく、本人もそれを認めている。この場合、誰もが意図的犯行と判断するだろう。裁判でも情状酌量の余地がない限り無罪にはならない。一方で、脳の科学的な研究による知見は加害者の行為が意図的ではないことを示している。もし、この科学的な知見が十分に信頼できるものであれば、加害者の行為は意図的ではなく刑事罰を科すことはできないということになる。 これをどう考えればよいだろうか。このような事例は現実にはありえない、脳の反応は必ず意図的な行動のパターンを示すと多くの者が主張するだろう。しかし、それを証明することができるだろうか。人々の脳の反応を常時詳細にモニターすることなど現実的には不可能であることは別にしても、証明はできない。なぜなら、意図という概念は脳の反応という自然科学的な領域には適用できないからだ。自然には意図など存在しない。人間もその一員である自然は「あるがままにある」。意図は人の行為を説明するために用いられる概念であり自然科学的な概念ではない。それゆえ、意図あるいは意図的であることを脳の反応のパターンから読み取ることはできない。意図的な行為を遂行する際に、脳には共通する特徴的なパターンが存在するかもしれない。だが、それが事実だとしても、血痕のDNA鑑定と異なり、脳内で生じたパターンを罪状認定の証拠に用いることはできない。脳内のパターンは意図あるいは意図的とは異質な次元の事象だからだ。 教師が生徒に「この問題が解ける人」と声をかける。解ける生徒は「手を上げる」。一方、教師から見ると「(生徒の)手が上がる」ということになる。しかし教師は生徒が意図的に手を上げたことが分かっている。つまり、意図とは行為主体の内的視点に関わるものであり、かつ、他者がそれを意図的と認める行為に係るものなのだ。それゆえ、意図とは共同体的な概念であり自然科学的な研究で正体や機序が分かるものではない。それゆえ意図的であることの基準は時代と共に、あるいは属する共同体の違いにより変わる可能性がある。 本稿の議論に何か意味があるのかと訝しむ者がいるだろう。意図や意図的という概念が含む深い意味など知らずとも、私たちは日常生活で困ることはない。意図的かどうかで争いになることはある。裁判で論点になることもある。だが、係争になっても、哲学的な議論など参考にすることはなく、物的証拠、関係者の証言、過去の判例などを基に実務的に解決される。こういう異論があろう。しかし、AIの進歩で、人間並みあるいはそれ以上の知能と規範遵守能力を持つアンドロイドが夢ではなくなっている。もしそういうアンドロイドが人を傷つけたとき、私たちはアンドロイドをどう処分すべきだろうか。アンドロイドに人を傷つけるようなアルゴリズムを組み込んだ開発者がいたとしたら、開発者を傷害罪として起訴すればよい。しかし完全な自動学習で人間と同等あるいはそれ以上の知識と規範を身につけたアンドロイドが傷害事件を起こした場合に開発者に責任を負わせる訳には行かない。ではどうするか。アンドロイドにも意図的という概念を適用し、意図的と判断される場合は刑事罰を科すというやり方が考えられる。しかし、アンドロイドの行為を意図的、非意図的と判別することができるのだろうか。そのようなことは不可能であり、アンドロイドが起こした事件はすべて機械の故障として扱うべきという考えもあろう。こういう問題を考えるうえで本稿の議論が役に立つ。その場合、意図や意図的とは共同体的な概念であるという点が鍵となる。 了
|