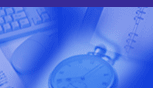

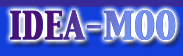
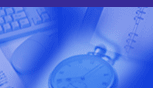 |
 |
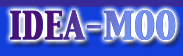 |
||||||||
|
井出 薫
ハイデガーは「存在(Sein)とは何か」という問いが哲学の第一問題だという。そして古代ギリシャ以来の西洋哲学=西洋形而上学は「存在とは何か」という問いと「存在者(Seiendes)とは何か」という問いの差異を看過してきたと指摘する。つまり「存在とは何か」という問いが、暗黙裡に「存在者とは何か」あるいは「存在者全体の性質は何か」という問いにすり替えられてきたという。そこでハイデガーは存在者ではなく、存在者の存在とは何かを問うと宣言する。存在者を了解するには、まず存在を了解する必要があるというのがハイデガーの論拠であり、尤もな意見でもある(異論はある)。 では存在並びに存在者とは何なのだろう。私の目のまえに机がある。机には様々な属性がある。形状、色、大きさ、重さ、材質など机そのものに備わった固有の属性の他、製造年月日や製造者、所有者、設置場所、使用目的なども付随的な属性として挙げることができる。では、これらの属性をすべて捨象すると何も残らず無になるのだろうか。多くの哲学者はそのような考えに同意せず、存在者あるいは存在する(在る)という何かが残ると考える。アリストテレスはそれを実体と表現している。 このことは、世界を構成するあらゆる事物に共通する「何か」が存在者あるいは存在する者であるということを示している。そして、存在者を存在者と呼ぶことができるのは「存在(在る)」が何らかの了解可能な意味を持つからに他ならない。だからこそ、存在(在る)を存在者に先立つ「何か」として捉え、それを問うことが哲学の第一問題だという議論が成り立つ。そして、この問いをとことん突き詰めることでハイデガーは20世紀最高の哲学者と称賛されるまでになった。 だが「存在とは何か」という問いは一体どのような問いなのだろうか。「存在とは何か」と問われても私たちは戸惑うばかりで何も言えない。ハイデガーは、それは存在の意味を問うことだという。そして、意味とは存在が了解されていることを示す。意味とは了解されることで初めて意味になるからだ。了解されない意味は意味ではない。意味とは常に了解(あるいは理解)と共にある。それゆえ存在への問いは、存在了解の在りようへの問いとなる。 主著『存在と時間』では、ハイデガーは存在を了解する人間存在の様態に力点を置いて考察を進める。存在には現実存在(実存)と本質存在という二面性がある。たとえば机では現実に存在するという側面と同時に、その形状や製造した目的など机の本質との関わりにおいて存在するという側面がある。人間でも基本的にはそれに変わりはないのだが、個人にとって自分が何のために世界に在るのかは分からない。親が生殖行為をしたから結果的に存在しているだけで、そこに何か使命のようなものはない。使命があったとしてもそれは隠蔽されており認識することはできない。それゆえ、人間は実存として自らを取り巻き自らがそこに棲む世界に被投され、不安を抱えながら世界と関り、他者との会話を通じて、暗黙裡に存在を了解して未来へと自らを投企して生きている。こうした在りようには自ずと時間という性格が付き纏う。そして各人は自身が不死の存在ではないことを、死の先駆的な覚悟性の中で了解し、運命を受け容れ、それを実践する。おおよそ、このような構図の中で存在了解がなされているとハイデガーは考える。そして、現代の存在了解は古代ギリシャ哲学に端を発する西洋形而上学の伝統において形成されたものであると指摘する。 ハイデガーの思想は時代と共に変化していく。『存在と時間』では、実存としての人間は特別な地位をもっていた。そして古代ギリシャ以来の存在了解の根源的な転換が計画されていた。だが、やがてハイデガーは実存としての人間が自らの力で存在了解の転換を成し遂げることはできないと考えるようになる。存在は自らその姿を現し、また隠蔽する。人間は存在に召喚され存在史の中で生きるのみであり、できることは「存在」を「存在の住処」である「言葉」に大切に収め、それを未来に送り届けることである、と論じるようになる。 結局、ハイデガーは「存在とは何か」という問いに答えを与えることはできなかった。むしろ、そのようなことは人間にできることではない、それがハイデガーの終着点だったとも言える。しかし、それならばハイデガーは不毛な試みを続けていたことになるのだろうか。確かに「存在とは何か」という問いそのものに関してはその通りだと思う。だが、ハイデガーは存在を問う過程で、存在者と存在の差異を見出し、近代社会における人間存在の様態を明るみにだし、近代の科学と技術が隠し持つ本質的に破壊的な性格を暴き出した。また伝統的な哲学の限界も示した。つまり存在への問いに最終的な答えを与えることはなかったが、その思索の過程において多くのことを成し遂げた。そして、ハイデガーの思索は、科学論、技術論、資本主義を核とする現代の世界像、近代の人間像など哲学的考察を要求する多くの分野に巨大な足跡を残し、ポストモダニズム、資本主義批判や科学技術批判で盛んに引用される思想となっている。 一方で、ハイデガーの哲学には批判も多い。ハイデガーの議論は非論理的で無意味だとする者は少なくない。「存在(在る)」とは数学や数理論理学で使用される存在量化記号「∃」に過ぎないと指摘する者がいる。カルナップは、その観点から『存在と時間』を無意味な言明が多数含まれると批判する。しばしばハイデガーと並ぶ20世紀最大の哲学者と評されるウィトゲンシュタインを引用してハイデガーを批判することもできる。たとえば前期ウィトゲンシュタインの『論考』を引用して「存在とは何か」は無意味な問いだと指摘することができるし、後期ウィトゲンシュタインの言語ゲームを引用して、「存在」とは言葉であり、その意味を知りたければ、それが言語ゲームの中でどのように使用されているかを調べなければならないと批判することもできる。このように「存在(在る)」は私たちが使う言葉又は記号の一つに過ぎず、それ以上でも以下でもない、それゆえ言語分析によりその役割や意味が解明されるものであり、ハイデガー流の難渋な哲学的思索で解明されるものではないという議論もできる。 どちらが正しいかは決められない。要は見方によると言うべきだろう。ハイデガーやその賛同者たちは、「存在(在る)」という言葉が関わる様々な事物(世界あるいは存在者全体を含む)を根源的かつ徹底的に哲学的に思索することを目指す。一方で「存在(在る)」を言葉の一つに過ぎないとする者たちは、それが言葉の体系の中でどのような役割を果たしているかに着目して言語分析や論理分析を展開する。つまり目指すところが違うので、探求の方法も、展開される議論の性格も大きく異なることになる。だが、いずれにしろ、「存在(在る)とは何か」を問うことには、その問い自体はたとえ無意味なものだったとしても、大きな意義がある。夜中人々が寝静まったあと、部屋で一人静かに「存在とは何か」と考えてみよう。様々な思索が広がっていくはずだ。ここでは取り上げなかったが、「なぜ人間はそのような哲学的な問いを問うのか」という疑問も浮かぶ。そして、その疑問からニーチェの哲学思想へと入っていくこともできる。 了
|